2025年07月01日
事業部制組織とは?
「事業部制組織」とは、経営陣(トップ・マネジメント)の下にある組織を事業部で分けた組織になります。分け方としては次のような方法があります。
1-1.製品・サービスで分ける。
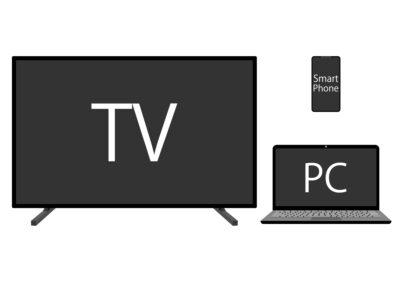
事業部制組織で下部組織を分ける一つ目の方法は「製品・サービス」で分ける方法です。
企業が扱う製品・サービスで事業部を分けるケースがこれに該当します。例えばA製品・B製品・Cサービスを扱う企業が、それぞれの製品・サービスごとに事業部を分ける場合などです。(A製品事業部・B製品事業部・Cサービス事業部など。)このように製品・サービスで事業部を分けることでそれぞれの事業部が単一事業のみを有する事業会社のようになります。
このように製品・サービスごとに事業部を分ける事で各事業部は自分達の担当する製品・サービスに特化した経営判断や戦略を行いやすくなります。例えば、A製品事業部はA製品の市場拡大、製造コストの最適化、販売促進戦略に集中でき、B製品事業部はB製品のブランド価値向上や新機能開発に専念できます。それぞれの事業部が独立した意思決定を行えるため、市場の変化や顧客ニーズに迅速に対応できる点が大きな利点です。加えて、製品・サービスごとの収益構造や利益率も明確になり、経営陣がどの事業が成長性や収益性に優れているかを容易に把握できるようになります。
更に製品・サービス別の事業部制は、担当者やチームの専門性向上にもつながります。各事業部のメンバーは同一製品・サービスに集中して取り組むため、技術的知識や市場知識、顧客理解の深さが増し、より高いレベルの提案や改善が可能になります。この結果、製品・サービスの品質向上やイノベーション創出のスピードも速まる傾向があります。特に多角的な製品ラインを持つ企業においては、各事業部が独自に戦略を練り、競合との差別化を図ることができるため、全社的な成長に寄与することになります。
一方で、製品・サービス別に事業部を設置する場合、事業部間で資源の取り合いが起こりやすくなる点には注意が必要です。例えば、研究開発費や広告費、人材などの有限なリソースをどの事業部に優先的に配分するかで社内調整が必要になります。しかし、これも経営陣が明確な優先順位を設定し、事業部ごとの目標や成果指標を適切に管理することで、効率的に解決可能です。
総じて、製品・サービスごとの事業部制は、各事業の特性や市場動向に応じた柔軟な経営が可能になる一方で、全社視点での調整力も求められる組織形態です。それぞれの事業部が「小さな独立企業」として機能することで、企業全体としての競争力や市場対応力の向上が期待できると言えます。
1-2.地域・エリアで分ける。

事業部制組織で下部組織を分ける二つ目の方法は「地域・エリア」で分ける方法です。
事企業が自社を地域・エリアで事業部を分けるケースがこれに該当します。例えば企業が米国・北海道・四国・韓国・中国で事業を展開しているとします。このケースで各事業をエリアごとに分類するのがこの方法になります。(米国支社・北海道支社・四国支社・韓国支社・中国支社など)このように地域・エリアで事業部を分けることで別地域にある企業が独立した小企業のようになります。
地域・エリアごとに事業部を分ける事で、それぞれの地域特性や市場環境に即した戦略を柔軟に立てられる点が大きな特徴です。例えば米国支社は現地の法規制、消費者嗜好、競合状況に合わせた販売戦略やマーケティング活動を独自に展開できます。一方で北海道支社は、日本国内の地域特性や物流条件、季節需要を踏まえた製品供給や販売計画を行うことが可能です。このように各地域が独立した小企業のように運営されることで、地域ごとのニーズに迅速に対応でき、競争力の向上につながります。また、地域ごとに売上や利益、コスト構造が明確になるため、経営陣はどの地域が成長性や収益性に優れているかを容易に把握し、戦略的な意思決定を行いやすくなります。
更に地域・エリア別の事業部制は現地の人材活用や組織文化の形成にも有効です。各地域事業部は独自のマネジメント体制や業務慣習を持つことができ、現地の従業員が地域の事情に精通した経営判断を行いやすくなります。特に海外進出している場合、文化や商習慣の違いを理解した上での意思決定が不可欠です。地域ごとの事業部が独立性を持つことで、こうした現地適応型の経営が可能になり、グローバル市場での成功確率を高めることができます。
一方で、地域・エリア別に事業部を設置する場合、各地域間での調整や情報共有が課題となる事もあります。例えば新製品の開発や広告キャンペーン、物流戦略など、全社的な統一方針との整合性を取る必要があるため、経営層のマネジメント力が求められます。しかし、明確な権限分掌と報告・連携体制を整備することで、地域ごとの独立性と全社戦略のバランスを保つことが可能です。
総じて、地域・エリア別事業部制は、地域ごとの市場環境や顧客ニーズに即した意思決定を可能にする柔軟な組織形態です。それぞれの事業部が独立して機能することで、地域市場での競争力向上や迅速な対応力の強化が期待できる一方、全社的な調整や統合戦略を適切に管理することが成功の鍵となります。
1-3.顧客単位で分ける。

事業部制組織で下部組織を分ける三つ目の方法は「顧客単位で分ける」方法です。
企業が顧客単位で事業部を分けるケースがこれに該当します。例えば企業が幾つかの主要な顧客セグメントに製品・サービスを販売しているとします。このケースで顧客単位でセグメントを分類するのがこの方法です。(50代以降、30~50代までの女性、20~30代の男性など)このように顧客単位で事業部を分けることで各事業部はそのセグメントに集中することができるようになります。
顧客単位で事業部を分ける事で、各事業部は自分たちが担当する顧客層のニーズや嗜好に特化した戦略を立てやすくなります。例えば、50代以降の顧客を対象とする事業部は、健康志向や品質重視の傾向を踏まえた製品開発やマーケティング活動を行うことが可能です。一方で、20~30代の男性を対象とする事業部は、トレンド性や利便性、デジタル活用を意識したアプローチを取ることができます。このように、顧客単位で事業部を分けることで、各事業部は特定の顧客層に最適化された商品・サービス提供やコミュニケーション施策を展開できるため、顧客満足度やブランドロイヤルティの向上につながります。
また顧客単位の事業部制は収益性やコスト構造の分析にも有効です。各事業部が特定の顧客層に焦点を当てることで、どの顧客セグメントが利益を生み出しているか、どのセグメントへの投資が効果的かを明確に把握できます。経営陣はこの情報をもとに、資源配分や成長戦略の優先順位を戦略的に決定できるため、企業全体の効率的な経営にも寄与します。
更に顧客単位での事業部制は、営業やマーケティング、サービス提供の専門性向上にもつながります。各事業部の担当者は特定の顧客層に精通することで、より深い顧客理解に基づく提案や改善が可能になります。これにより、顧客の潜在ニーズに対応した新製品開発やサービス改善が加速し、競合他社との差別化も図りやすくなります。
一方で、顧客単位で事業部を設置する場合、事業部間での製品やサービスの重複、資源の分散などが起こりやすい点には注意が必要です。例えば、同じ製品を異なる顧客層向けに展開する場合、開発や生産、マーケティングの効率性が低下する可能性があります。しかし、各事業部の目標や役割を明確化し、全社的な調整を行うことで、こうした課題は十分に管理可能です。
総じて、顧客単位での事業部制は、顧客セグメントごとの最適化を可能にする組織形態です。各事業部が特定の顧客層に集中することで、サービスや製品の質の向上、顧客満足度の向上、収益性の改善が期待できる一方、全社的な調整や資源配分のバランスを取ることが、成功の鍵となります。
事業部制組織:まとめ
上記の通り事業部制組織は機能別組織とは異なる組織形態になります。MBA受験に向けて、これらの違いをしっかりと理解した上で組織について考えられるようになって下さい。事業部制組織の特徴は別記事で解説していますので、こちらもご一読下さい。「事業部制組織のメリット・デメリット徹底解説|MBA視点で導入前に押さえる3つのポイント」