2025年05月05日
目次
SCP理論とは?
「SCP理論」とは業界構造が最終的に企業の業績を決めるという理論です。「SCPモデル」とはその考えを反映したモデルになります。そのSCPの詳細はそれぞれ以下の通りになります。

1-1.業界構造(Structure)
SCPモデルの「S」は「業界構造(Structure)」になります。これには「競合企業の数」「製品の違いの程度」「参入・退出コスト」等があります。例えば競合の数が多ければ競争によって利益率は下がりますし、競合間で同じような製品が多ければその分だけ競争が激しくなり利益率は下がります。またその業界の参入・退出コストが低ければ出入りが容易なので多くの企業が参入してきます。これが業界構造になります。企業の利益率は業界構造に影響を受けてしまうのです。つまり業界構造は次の企業行動に直接的な影響を与えます。
業界構造は企業の意思決定に直接的な影響を与えます。例えば競合が多く利益率が低い市場では、価格競争を避けるために差別化戦略が求められます。製品差別化の程度が高ければ、企業は独自の製品・サービス提供を通じて収益性を高めやすくなります。また競合が少ない特定の寡占市場のように参入障壁が高い市場では、新規参入者が行われないので長期的な投資やブランド構築が可能です。更に独占市場であれば無理に競争する必要がないので価格を高く設定し高い収益性を維持する事ができます。このように業界構造は単に市場の状態を示すだけでなく、その中で企業がどのような行動を取るか、企業が採用する戦略の内容を決定づける重要な制約条件になります。
1-2.企業行動(Conduct)
SCPモデルの「C」は「企業行動(Conduct)」になります。企業は業界構造に基づき取るべき行動を判断します。これには「需要変動への動き」「差別化」「談合」等があります。例えば市場価格が何らかの原因により低下した場合に、競合の数が多ければ、価格を下げるしかありません。(このような動きを取る企業を「プライステイカー」と言います。)また多くの企業が均質性の高い製品を扱っている場合、企業は少しでも利益率を高めようと製品差別化のような動きを取ります。また業界の利益率を高めるために談合(独占禁止法違反です。)を行い、業界全体の利益率を維持することがあります。この企業行動が企業のパフォーマンスに影響を与えます。
企業行動は業界構造という制約がある中で利益を最大化するための意思決定を指します。価格設定や製品差別化だけでなく、広告・販促活動、研究開発投資、提携・買収戦略なども含まれます。例えば企業は競争が激しい市場では製品やブランドを強化して競合と差別化することで市場シェアの維持・獲得を行います。また企業が独自技術や独自サービスを提供することで業界内で移動障壁を作り長期的な優位性を築くことも可能です。また独占市場であればむしろ価格を限界まで高める事や独占状態の維持に集中すると思います。このように企業は業界構造に応じて企業行動を決定します。
1-3.パフォーマンス(Performance)
SCPモデルの「P」は「パフォーマンス(Performance)」になります。企業の業績は企業行動により決まります。しかし企業が取れる行動は業界構造により制約を受けており、結果的にパフォーマンス(業績)は業界構造により決定すると考える事ができます。これがSCPモデルの基本的な考え方です。企業のパフォーマンスには、売上や利益率、成長率、効率性などが含まれます。また、顧客満足度や市場シェアといった指標も重要であり、企業行動の成果を多角的に評価することが重要です。
パフォーマンスは財務的な結果に留まらず長期的な競争優位の確立や市場全体への影響も重要になります。例えば価格競争が激しい市場では利益率が低下する一方で、製品差別化やブランド構築に成功した企業は高い収益性を維持できます。そのため長期的に収益が獲得できるパフォーマンスが重要になります。また業界構造に応じた企業行動は業界全体の健全性や成長性にも影響を与えます。何故なら企業が取るパフォーマンスにより業界の環境が変化するからです。競争の激しい業界で多くの企業が不正な手段に手を染めれば業界全体の魅力度は下がります。また逆に業界内の多くの企業が製品差別化に成功すれば業界全体が成長しますし、逆の場合は業界全体が衰退していきます。このようにSCPモデルでは業界構造が企業行動を通じてパフォーマンスに結びつき、そしてそのパフォーマンスが業界の状態や環境を決定します。SCPモデルは業界を分析するフレームワークとして利用されます。
業界の競争構造
業界の競争構造は以下の四種類に分類することができます。業界が次のどの状態にあるかによって企業の利益率は大きく変化します。
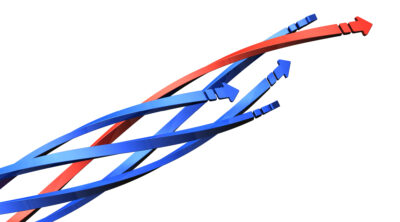
2-1.完全競争
まず一つ目は「完全競争」になります。完全競争とは数多くの競合企業があり、それらが類似性の高い製品を扱っており、参入・退出コストが低い状態の事を言います。つまりこのような状態では企業は利益を出すのが難しいと言えます。何故ならほとんど全ての企業がプライステイカーとなっている状態だからです。企業にとっては最も苦しい競争構造になります。しかし社会的厚生という視点から見ると、これは最も魅力的な状態だと言えます。完全競争では価格は市場の需給で決定されるため、企業は自由に価格を設定できません。その結果として効率的な資源配分が行われて消費者は低価格で同水準の製品を手に入れることができます。社会全体としては、無駄の少ない最適な市場構造と言えます。
2-2.独占的競争
次に二つ目は「独占的競争」になります。独占的競争とは多数の競合企業があり参入・退出コストが低いところまでは完全競争と同じですが、企業が差別化された製品を扱っているという点が異なります。この状態では企業が差別化された製品を扱っているので、擬似的に独占企業のような行動を取ることが可能です。例えば特定のセグメントに模倣困難性の高いシャンプーを開発した企業は、そのニッチなセグメントにおいては独占企業のように行動することが可能です。しかしその地位は常に競合企業に脅かされているのも、この競争構造の特徴になります。独占的競争では各企業が独自のブランドや製品で差別化を図るため、価格や品質にある程度の裁量があります。しかし参入障壁が低いため成功している市場セグメントには常に新規参入者が現れる可能性があり、既存企業は継続的にイノベーションやマーケティングを行わなければなりません。このため企業の利益は安定しにくく競争環境は常に変化しています。
2-3.寡占
三つ目は「寡占」になります。同質の製品を扱う競合他社が少数しかいないという状態です。参入・退出コストは高く、企業にとっては魅力的な状態になります。何故なら参入障壁が高く、少数の競合しかいないので、競争が極めて緩やかになる為です。またこのような状態では業界上位の数社がシェアの大半を占めているので、暗黙的談合により競争を減らす事ができます。(暗黙的談合は別記事で解説します。)寡占市場では企業は価格や生産量などの戦略を互いに意識しながら調整したように行動します。例えば現代の携帯電話業界などが該当します。このため暗黙的な相互依存が生まれ企業の意思決定は単独ではなく市場全体の動きに左右されます。また技術革新やマーケティング施策によって優位性を築けば長期的に高い利益を維持しやすく、業界全体の安定性や収益性が高まる傾向があります。
2-4.独占
最後の四点目は「独占」になります。その製品・サービスを扱う業者が一社だけであり、高い参入コストが発生する業界です。基本的に独占は独占禁止法という法律で禁じられていますが、それに近い状態の企業はあります。例えばマイクロソフト社のOSは独占に近い状態となっています。これは企業にとっては最高の状態です。何故なら顧客はそのサービス・製品を買うしかなく、企業は価格を高める事が用意になるからです。しかし社会的厚生は最も低くなります。顧客としても企業が独占状態だと、競争がないので良いサービス・製品が望めなくなり、高い価格を受け入れざるを得なくなります。更に独占企業は市場全体を支配するため、技術革新やサービス改善などの努力意欲が低下する可能性があります。その結果、長期的には市場の停滞を招くことがあり政府による監視や競争促進が重要となります。
SCPモデルと競争構造:まとめ
上記の通り業界構造や競争構造は企業の業績に大きな影響を与えます。その意味で企業にとっては魅力的な業界とそうでない業界があると言えます。そのため新規参入の前にはこれらをしっかりと分析する必要があります。業界構造と競争構造は非常に重要なコンセプトになりますので、MBA受験に向けてしっかり理解しておくようにしましょう。