2025年06月16日
戦略的提携のメリット・デメリットとは?
別記事(「MBA受験に役立つ戦略的提携の基礎知識|3つのタイプとその違い。」をご覧下さい。)で戦略的提携について解説させて頂きましたが、戦略的提携にはメリットとデメリットがあります。詳細はそれぞれ以下の通りになります。
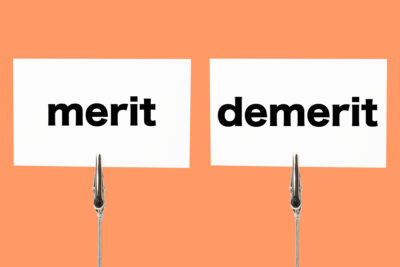
1-1.戦略的提携のメリット
「戦略的提携のメリット」は次の通りです。
1.競争力の向上
一点目は「競争力の向上」になります。戦略的提携を行う事で企業は自社にはない経営資源を獲得することができます。例えば自社に特定の製品を製造する技術がなかったとしても、その技術を持つ企業と提携すれば、その技術を利用することができるようになります。このように戦略的提携を行う事で企業は市場での競争力を向上させる事が可能となります。更に戦略的提携は単に技術や資源の共有に留まらず、マーケティングチャネルや販売網の拡大にも役立ちます。これにより新規市場への参入や製品の認知度向上が容易になり、競争優位性を強化する事ができます。またリスクやコストを分散できる点も大きなメリットです。
2.コスト削減
二点目は「コスト削減」になります。戦略的提携を行う事で企業はコスト削減を実現できるようになります。何故なら規模の経済や範囲の経済を実現する事が容易になるからです。また相手企業の経験が豊富であれば経験効果によるコスト削減を実現できる可能性もあります。このように戦略的提携でコスト削減を実現する事が可能です。加えて共同での研究開発や製造、物流の効率化により固定費や変動費を抑えることができます。更に仕入れや調達を提携先と統合することで購買力を高めて、材料費や外注コストを低減する事も期待できます。このように戦略的提携は多方面でのコスト削減効果があります。
3.市場拡大・参入が容易になる。
三点目は「市場拡大・参入が容易になる」点になります。戦略的提携を行う事で企業は市場拡大・参入が容易になります。例えば提携する企業の販売ネットワークや顧客基盤を利用することができれば、より多くの顧客にアプローチすることができるようになります。またドメスティックな企業が海外の企業と提携すれば、海外展開が容易になります。このように戦略的提携で市場拡大・参入が容易になります。更に戦略的提携は現地の法規制や文化的な障壁を乗り越える支援にもなります。提携先のノウハウや信頼関係を活用することで、新市場でのリスクを低減し、短期間での事業を展開する事が可能になります。結果として、企業は効率的かつ戦略的に国内外での市場拡大を実現する事ができます。
4.リスク分散
四点目は「リスク分散」になります。戦略的提携を行う事で企業はリスクを分散する事ができるようになります。複数の企業と提携する事で、新製品開発のリスクや特定の市場や顧客に依存するリスク、また投資のリスクなどを分散することができるようになります。更に提携により財務負担や事業運営の不確実性も分散されます。例えば新規市場への投資や技術開発において、単独で行うよりも損失リスクを低減できます。また提携先の専門知識や資源を活用することで、事業の安定性を高め、長期的な成長戦略を安全に進めることが可能となります。
5.イノベーションの促進
五点目は「イノベーションの促進」になります。戦略的提携を行う事で企業はイノベーションを促進する事ができるようになります。一般的に同質的な組織からイノベーションを生み出すのは難しいとされています。しかし複数の企業が提携すればそれぞれの違いを活用しやすくなるので、イノベーションを生み出す事が容易になります。加えて異なる企業の知識や技術・経験を組み合わせることで、新しい製品やサービスの開発スピードが向上します。異業種間の提携では特に既存の枠にとらわれない発想や新市場の創出につながるケースも多くあり、競争優位性の確保や差別化戦略の実現にもつながります。
1-2.戦略的提携のデメリット
「戦略的提携のデメリット」は次の通りです。
1.シナジー効果が発生しない。
一点目は「シナジー効果が発生しない」点になります。戦略的提携を行ってもシナジー効果が発生しない可能性があります。これは目標やビジョンが一致しなかったり、相手先企業の行動が期待通りでなかった場合に起こります。また想定外のトラブルが生じた結果、シナジー効果が発生しない事もあります。更に企業文化や経営スタイルの違いが摩擦を生み、企業同士の協力関係が円滑に進まない場合もあります。コミュニケーション不足や情報共有の不十分さもシナジーを阻害する要因になります。そのため提携効果を最大化するには事前の調整や継続的なマネジメントが不可欠となります。
2.情報漏洩のリスク
二点目は「情報漏洩のリスク」になります。戦略的提携を行った場合、情報漏洩のリスクが生じることになります。自社の技術や能力、顧客情報などを他の企業と共有すると、その情報を漏洩するリスクは高まります。秘密保持契約を結ぶ事で情報漏洩リスクを軽減することはできますが、その内容が守られない場合や、相手先企業の過失による情報漏洩のリスクを完全に無くす事はできません。加えて提携先の従業員や取引先を通じた間接的な情報流出も懸念されます。特に競合他社との関係がある場合、意図せず機密情報が外部に伝わるリスクが高まります。そのため情報管理体制の強化やアクセス権限の明確化など継続的なリスク対策が重要になります。
3.意思決定の遅延
三点目は「意思決定の遅延」になります。戦略的提携を行った場合、複数の企業と業務を進めていくことになるので、意思決定の遅延が生じることになります。特に相手先企業の意思決定に時間が掛かる場合や、相手先企業と意見が一致しない場合はこの事態が生じやすくなります。更に意思決定の遅延は市場対応のタイミングを逃す原因にもなります。迅速な行動が求められる新規事業や競争環境の変化において、提携企業間で調整に時間を要することで、ビジネスチャンスを失うリスクも増加します。そのため効率的な意思決定プロセスの構築が不可欠になります。
4.相手先企業のリスクを抱える事になる。
四点目は「相手先企業のリスクを抱える事になる。」という点になります。戦略的提携を行った場合、相手先企業のリスクも抱える事になります。例えば相手先企業が不祥事を犯した場合、または何らかのトラブルに巻き込まれたり経営不振に陥った場合、提携している企業はその影響を被ることになります。更に相手企業の信用低下や財務問題は、自社のブランド価値や市場での評判にも影響を与える可能性があります。また相手企業の戦略変更や提携解消により、事業計画や投資回収に支障が生じる場合もあります。そのため提携先の選定やリスク管理は慎重に行う必要があります。
5.関係性の維持に努める必要がある。
五点目は「関係性の維持に努める必要がある。」という点になります。戦略的提携を行った場合、相手先企業との主導権争いや関係性悪化によるリスクを抱える事になります。例えば自社で実行したい計画があっても、相手先企業の許可が必要である場合は、独断で計画を進めることができません。そのため常に相手先企業との関係性の調整に努める必要があります。関係性が悪化した場合は提携解消となりますが、提携解消時にも合意形成が必要なので、関係性が悪化しないよう常に相手先企業との関係性を良好に保てるよう努める必要があります。加えて主導権争いが長引くと意思決定や事業推進が停滞し、競争優位性を損なう可能性もあります。契約内容や権限範囲を明確化するだけでなく、定期的なコミュニケーションや信頼関係の構築が不可欠です。こうした取り組みにより提携の安定性を維持し、双方にとってメリットのある協力関係を継続する事ができるようになります。
戦略的提携のメリット・デメリットとは?:まとめ
上記の通り戦略的提携にはメリットとデメリットがあります。戦略的提携について考える時に、自分の意見の根拠がしっかり述べられるよう、上記のメリット・デメリットを正しく理解しておきましょう。