2025年06月26日
階層構造とマネジメントの三要素
1-1.階層化
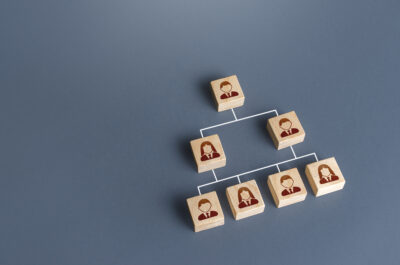
組織の「階層化」とは、中間管理職を入れることで組織の階層が増えていく事です。
組織の階層は従業員が増えれば必ず必要になります。例えば5人の会社だと社長とそれ以外のメンバーで直接やり取りをすれば充分です。しかし50人の会社になれば、社長が全ての従業員に直接指示を出すのは非効率です。何故なら50人もいれば常に全員の動きを把握することが難しいからです。そのため階層を作る事になります。例えば社長を含む50人の組織であれば、残り49人を7人×7つの組織に分けることなどが考えられます。もちろん職種や担当する内容により分けるべきなので、数字だけで判断することはできませんが、基本的には下部組織を分けることになります。しかしその際は統制の幅に気を付ける必要があります。
階層化の本質は組織の成長と合わせて情報や指示の流れを整理し、効率性と明確な責任体制を確保する事にあります。規模が小さい段階ではトップとメンバーが直接やり取りできるため、意思疎通も迅速で柔軟です。しかし、従業員が増えると情報が錯綜し、トップの負担が急増します。このとき階層を導入することで、指揮命令系統を整理し、誰が誰に報告し、誰が意思決定を下すのかを明確にできます。
また階層化は単なる人数の分け方ではなく役割や責任の分担を反映する仕組みでもあります。例えば営業、製造、企画といった職能ごとに中間管理職を置くことで、専門性を活かした組織運営が可能になります。更に階層を設けることで、社員は直属の上司に相談できる環境を得られ、社長が全員の細部に関わらずとも組織は機能します。
一方で階層が増えるとデメリットも生じます。伝達経路が長くなれば情報の遅延や歪曲が発生しやすく、現場の声が経営層に届きにくくなります。更に中間管理職が多すぎると「指示待ち文化」が定着し、柔軟な意思決定が阻害される恐れもあります。したがって、階層化を進める際には、組織の規模や事業内容に応じて「必要最小限」にとどめる工夫が求められます。
MBAで学ぶ際は階層化を組織の成長に伴う自然な減少と捉えると共に、その副作用をどう抑えるかに着目する事が重要です。すなわち、階層を作ること自体が目的ではなく、組織の効率性や柔軟性を高めるための手段である、という視点を持つことが求められます。
1-2.統制の幅
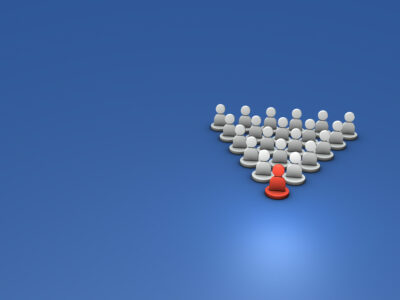
「統制の幅」とは、一人の管理者が処理・コントロールできる数には限界がある事を言います。
基本的に管理者が一人で全ての部下をコントロールするのは不可能です。先ほどの例で社長を除く49人の組織を分けるにしても、例えば2つの組織にして、片方を42人、もう片方を7人とすれば効率的な運営は見込めなくなります。何故なら現実問題として階層化しても41人(42人組織からリーダー1人を除く)のメンバーに一人のリーダーが直接指示を出すのは難しいからです。そのため階層化する時には統制の幅を意識する必要があります。一般的に統制の幅は5~8人程度と言われています。そのため例えば先ほど挙げた通り7人×7つのチームに分けることなどは統制の幅という観点からは非常に合理的な方法だと言えます。しかし最も重要なのはその後に権限移譲することです。
統制の幅を考える際に重要なのは単なる人数の多寡ではなく業務の性質や部下の熟練度、組織文化などの要素を総合的に捉える事です。例えば、業務が標準化され、マニュアルに沿って比較的単純に進められる作業であれば、一人の管理者が10人以上を監督することも可能です。逆に、業務内容が複雑で高度な判断を要する場合や、新人が多く教育的なフォローが欠かせない場合には、統制の幅は5人程度が限界となることもあります。
また情報通信技術の発達によりオンラインツールを通じて進捗状況や指示を効率化できるようになりました。それにより統制の幅をある程度広げても円滑に運営できるケースも増えています。しかし、どれほどツールが進化しても、部下のモチベーション管理や人間関係の調整といった側面は依然として管理者の重要な役割であり、この点では「直接の人間的接触」を欠かすことはできません。
更に統制の幅は組織構造そのものに大きな影響を与えます。幅が広すぎると管理者の負担が過大になり、結果としてリーダーシップの質が低下します。一方、幅を狭めすぎると階層が多くなり、組織が官僚化しやすくなります。このバランスをどうとるかは、組織設計における大きな課題です。MBAで学ぶ組織論では「状況適合理論」という考え方が重視され、最適な統制の幅は普遍的に決まっているわけではなく、環境や戦略に応じて変化するものとされています。
したがってリーダーは統制の幅を固定された数値として捉えるのではなく自組織の現状や目標に合わせて柔軟に調整する姿勢が求められます。そのうえで、適切に権限を移譲し、各管理者が自律的にチームを運営できる体制を整えることが、組織全体の効率性を高める鍵となります。
1-3.権限移譲

「権限移譲」とは、中間管理者に権限が委譲される事を言います。
権限を委譲することにより上位管理者の負担は軽減されます。企業が階層化して下部組織を作った後は下部組織のリーダーを任命する必要があります。例えば先ほどの例で50人の組織であれば、1人が社長、残りの49人を7人×7つの下部組織で分ければ、社長の下に7人の下部組織のリーダーがいることになります。これらのリーダーに社長の一部の権限を委譲することで、社長の負担は軽減されることになります。大企業になればなる程、各部門の長がその部門の意思決定権を有してるのは常識です。そのため権限委譲は必ず必要になります。またこの例では下部組織のリーダーが7人なので、社長の統制の幅の範囲内ですが、これが例えば10人となればもう一つ間に階層(複数の下部組織を束ねる組織)が必要になります。このように組織は数が増える度に階層化と権限委譲が行われていきます。
権限委譲において重要なのは単に仕事を任せるのではなく責任と権限のバランスを整える事です。権限だけを与えず責任ばかりを押し付ければ、リーダーは判断できずに形骸化した存在になってしまいます。逆に、権限だけが大きすぎて責任の所在が曖昧になると、組織全体の統制が効かなくなり混乱を招きます。そのため、権限移譲は「どの範囲まで決定してよいのか」「どこから上層部の承認が必要なのか」を明確にすることが欠かせません。
更に権限移譲はリーダーの育成にも直結します。部下に判断を委ねることで、管理職候補者は実践的な経験を積み、自らのリーダーシップを鍛えることができます。逆に、経営層が細部にまで口を出し続ければ、部下は受け身になり、主体性や問題解決力が育ちません。長期的に見れば、権限移譲の巧拙が組織の成長スピードを大きく左右すると言えます。
しかし権限移譲を行っても任せきりで良い訳ではありません。上位管理者は全体の方向性を示しつつ、必要に応じて進捗を確認し、サポートする仕組みを整える必要があります。いわゆる「管理の仕組み」と「信頼関係」があってこそ、権限移譲は機能します。
MBAの学びでは権限移譲は単なる作業分担ではなく組織の持続的成長を支える戦略的プロセスとして扱われます。組織が大きくなるほど、全ての判断をトップが担うことは不可能です。そのため、いかに適切に権限を分散させ、同時に全体としての一体性を保つかが、優れたマネジメントの条件であると言えます。
階層構造とマネジメントの三要素:まとめ
企業は拡大の過程で必ず階層化・権限委譲を行っていく事になります。またその際は常に統制の幅を意識する必要があります。そのためMBA受験に向けてこれらの内容はしっかりと覚えておくようにしましょう。そして経営組織について検討する時はこれらを常に意識しながら思考するようにしましょう。