2025年07月07日
キャッシュフロー計算書の三区分
キャッシュフロー計算書には以下三つの区分があります。それぞれの詳細は以下の通りです。
1-1.営業活動におけるキャッシュフロー

まず「営業活動におけるキャッシュフロー」とは、企業の本業である営業活動における現金の動きを表します。営業活動によるキャッシュフローは「直接法」と「間接法」の二つに分けることができます。
まず「直接法」とは実際の現金の収入と支出からキャッシュフローを計算する方法です。例えば売上が現金で入ればプラス、経費を現金で支払ったらマイナス、という形で一定期間の現金の収支を作成していきます。この方法では実際に現金の動きを伴った内容だけ記入していくことになります。当然ですが、直接法で計算した現金の残高は実際に手元に残った現金と一致します。何故なら現金の収支だけを基にキャッシュフローを計算しているからです。売上が売掛金(つまりまだ未回収)なら付けない、支払いが先でまだ現金で支払っていないなら付けない、というように現金ベースで計算したキャッシュフローを直接法と言います。
次に「間接法」とは損益計算書で計算した当期純利益から各種の項目を調整してキャッシュフローを算出する方法です。間接法は当期純利益から出発してキャッシュフローを計算していきます。例えば減価償却費は実際に現金は支払っていないので当期純利益にプラス、売掛金の未回収分は当期純利益に含まれているがまだ回収できていないのでマイナス、買掛金の未払分は当期純利益から引かれているがまだ支払っていないからプラス、というように当期純利益を実際の現金の動きに合わせて調整していきます。これが間接法になります。実務では圧倒的に間接法の方が多く採用されています。何故なら間接法の方が損益計算書とのつながりが強く、分かりやすいからです。また間接法は既に作成した財務諸表を基に計算するので非常に計算しやすくコストが安いという特徴があります。既に算出した当期純利益や売掛金・買掛金・減価償却費などの値をベースに作成するので、財務諸表が出来上がっていればキャッシュフロー計算書は比較的簡単に作る事ができます。そのため実務では間接法が採用されているのです。
1-2.投資活動におけるキャッシュフロー
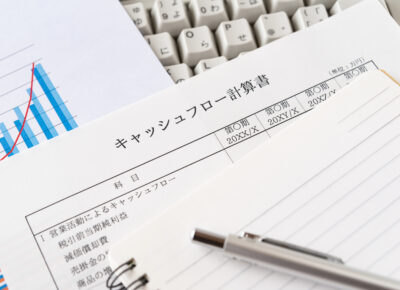
次に「投資活動におけるキャッシュフロー」とは、企業の投資活動から生じる現金の動きを表します。
企業の投資活動とは損益を伴わない交換取引の事です。例えば有価証券の売買や固定資産の売買などがこれに該当します。有価証券を購入すれば現金はマイナス、有価証券を売却すれば現金はプラスになります。また固定資産を購入すれば現金はマイナス、固定資産を売却すれば現金はプラスになります。ここで重要なのは損益が無関係な取引でも投資活動におけるキャッシュフローには計上されるという点になります。何故ならキャッシュフロー計算書は現金の動きを記入するものだからです。有価証券や固定資産の購入で現金の動きが伴った場合は必ずこの投資活動におけるキャッシュフローに計上する必要があります。例えば現金で特定の有価証券を購入すればその動きをここで計上します。しかし例えば有価証券の売却時に損益が発生した場合は、現金の動きだけここに記入する必要があります。(損益は損益計算書に記入します。)その意味で損益計算書とは異なる動きをするのが投資活動におけるキャッシュフローになります。
しかし投資活動であっても現金の動きが伴わない場合はキャッシュフロー計算書に記入する必要はありません。例えば車を購入し全額分割払いで契約した場合、この時点では「車(資産)・借入金又はリース債務(負債)」が増加しただけなので、キャッシュフロー計算書に記入する必要はありません。実際に現金の動きはありませんよね。ただし例えば土地や建物を購入し、借入金でこれらを購入した場合はキャッシュフロー計算書に記入する必要があります。何故なら「金融機関→企業→土地・建物の売主」と実際に現金の動きが起こっているので、企業は「借入金よる現金増加(財務活動)」と「土地建物購入による現金減少(投資活動)」を計算書に記入する必要があります。(借入金による現金増加は財務活動のキャッシュフロー計算書に記入します。)これが投資活動におけるキャッシュフローになります。一般的に投資活動におけるキャッシュフローはマイナスになります。何故なら企業は将来の収益獲得に向けた支出を行うのが普通だからです。 そのためこの特徴もしっかり理解しておいて下さい。
1-3.財務活動におけるキャッシュフロー

最後に「財務活動におけるキャッシュフロー」とは、企業の財務活動から生じる現金の動きを表します。
財務活動におけるキャッシュフローは、企業の財務活動から生じる現金の動きを表します。例えば借入金の増加、社債の発行、配当金の支払い、株式の発行などで現金に増減が発生した場合などがこれに該当します。これらは企業の営業活動や投資活動と異なり、企業が外部からお金を調達又は返済する行為となります。つまり財務活動におけるキャッシュフローは企業に直接的な損益をもたらすものではありません。例えば借入金を増加させて現金が増えても交換取引なので損益は発生しません。(もちろん有利子負債の利息支払い時には損益が発生します。)また配当金を支払っても、それは利益を株主に還元しているだけなので、損失が発生する訳ではありません。また社債や株式の発行でお金を集めても同じです。お金は増えていますが、利益が発生している訳ではありません。つまり財務活動によるキャッシュフローの増減は直接的に企業の損益に結び付く訳ではないのです。また財務活動におけるキャッシュフローががプラスであれば企業はその期間に多くの資金を調達している状態であり、マイナスであれば企業が配当の支払いや負債の返済を行っていることを意味します。このいずれが良い状態なのかは企業の状況やフェーズによると言えます。
財務活動におけるキャッシュフローの特徴は大きな金額が動くことです。例えば借入金の増加や社債の発行は現金を大きく増加させます。一般的に企業が利益で現金を増加させるのは非常に難しい行為になります。何故なら利益は全ての経費を支払った後、税金まで引いて手元に残ったものなので、売上の数パーセントになる事が一般的です。また企業は投資活動も行っているのが普通なので、残った利益から投資を行うと手元に大きな現金を残すのは非常に難しいと言えます。しかし財務活動では比較的大きなお金を集める事が可能です。例えば株式の新規発行を行えば現金を大きく増加させる事が可能です。借入金をしても大きな現金を集める事ができます。当然、株式の発行と異なり借入金の増加ような負債の増加は大きな現金支出を伴いますが、同じく大きなお金を集める事が可能な手段であるとも言えます。そのため財務活動におけるキャッシュフローの特徴は、大きな金額が動くことだと理解しておいて下さい。
キャッシュフロー計算書の三区分:まとめ
以上がキャッシュフロー計算書の三区分の詳細になります。キャッシュフロー計算書を作成するには上記の理解が不可欠ですので、これらについてしっかりと理解した上で覚えておくようにしましょう。またキャッシュフロー計算書は企業経営では貸借対照表や損益計算書より重要であるとも言えます。何故なら損益が黒字でもキャッシュフローが赤字だと企業は倒産するからです。そのためこれらのコンセプトをしっかり理解して企業の財務判断ができるようになりましょう。