2025年05月11日
経営資源の模倣がコスト上の不利となる理由
競合他社は競争優位にある企業の経営資源・能力を模倣しようとします。しかし一般的に「単に模倣するとコスト上の不利」となります。その理由は次の四つになります。
1-1.歴史的条件

まず特定の企業が低コストを実現した理由として「歴史的条件」が関わっている場合があります。
特定の時代に特定の資源へのアクセスを獲得した企業と同じ低コストを実現するには、その時代に戻り同じ条件が整わないと難しい場合があります。更に言えば特定の環境の下で磨く事ができた能力も、同じく別の環境下でも磨き上げる事ができるとは言い切れません。そのためこのような時期に低コストの源泉を獲得できた企業は低コストの構造を築く事ができますが、別の時期に模倣した企業は同じようなコスト構造を実現する事ができません。また経路依存性がある場合も同じだと言えます。
更に企業が低コストを実現する過程では単なる設備や技術の導入だけではなく時間を掛けて蓄積してきた経験やノウハウも大きな役割を果たします。例えば製造ラインの効率化や仕入れルートの最適化は、一朝一夕で獲得できるものではなく、長期的な試行錯誤や改善活動を通じて初めて実現できる状態です。このため同じ技術や設備を後から導入した企業が、元の企業とそのまま同等のコスト削減を実現することは非常に困難であると言えます。
また組織文化や人材のスキルも低コストの源泉になります。例えば現場での改善が日常的に行われる文化や、高いスキルを有した従業員による効率的な作業は、他社が容易に模倣する事はできません。更にこれらの能力は特定の歴史的・環境的条件の下で実現されてきたものであるので、同じ条件が揃わなければ同じ成果は期待できないと言えます。
このように低コストの達成には歴史的条件と累積した経験が関係していると言えます。結果として特定の時代に有利な条件を得た企業は競争優位を長期間維持することが可能ですが、後発企業は同じ方法では成功できません。この現象は経路依存性として戦略論でも重視されます。(経路依存性とは企業がこれまでに歩んできた経路や蓄積した経験が将来の選択肢や成果に大きく影響することを意味します。)つまり過去の歴史や積み上げた能力が、その企業の現在の競争力になっているのです。
1-2.因果関係不明性
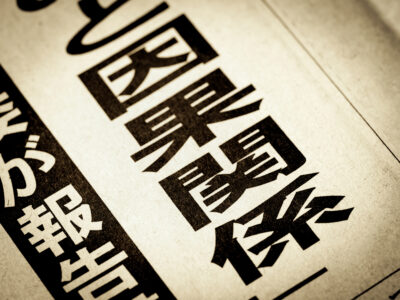
次に「因果関係不明性」を挙げる事ができます。
これは文字通りの意味になりますが、要するに特定の企業が競争優位を模倣しようとしても、その競争優位の源泉を理解できない場合は同じく模倣が困難になります。例えば組織文化や人間関係、仕入先や顧客との関係など、外側から理解しにくい競争優位は場合によっては実現している企業すら理解できておらず、無理に模倣しても同じような低コストを実現する事が出来ません。またそれが特定のプロセスだけではなく全体に価値が分散している場合、競合他社にとっては極めて模倣が難しくなります。そのため表面的な強みだけ模倣した場合、コストの構造は全く異なるものとなります。
更に企業の競争優位は複数の資源や過程が関係して価値を生み出しています。例えば優れた仕入先との関係や顧客関係、内部の意思決定プロセス、従業員の暗黙知や信頼関係などは、単独で存在しても同じ成果を生まないことが多いです。これらの要素は時間をかけて構築され、組織全体に浸透して初めて低コストや高付加価値といった競争優位につながります。そのため外部から観察しただけでは、その複雑な相互作用や因果関係を正確に把握することは非常に困難であると言えます。
また競争優位の源泉が企業内部の文化や習慣・従業員のスキルに根差している場合も模倣が難しいものになります。何故なら模倣しようとしても同じ環境や組織構造を再現することは簡単ではないからです。更に特定のプロセスだけを模倣しても、全体の価値創造の中での役割や関係を理解していなければ、同じく高い成果を挙げる事はできません。結果として表面的な模倣は失敗に終わる可能性が高くなり、コスト構造や効率性は大きく異なるものになります。
このように因果関係が不明であると他社にとって模倣が極めて難しいものなります。競争優位性を実現するには、他社の競争優位の源泉を正確に理解し、それが実現できると判断できれば実行すべきであると言えます。しかし単なる技術や手法を模倣すると失敗に終わる可能性が高くなるので、組織全体の構造や文化、歴史的背景をしっかりと分析する事が重要になります。
1-3.社会的複雑性

また特定の企業が「社会的複雑性」を有している場合も同じく模倣が困難になります。
企業が人材育成において特定の方法を採用している場合、その方法を模倣できたとしても、同じような結果を出せるとは限りません。何故なら人材育成を行う人の特性が効果的な人材育成を可能としている場合、競合他社はそれを理解する事も模倣する事もできないからです。このように競争優位が社会的複雑性を有している場合も模倣する事が困難だと言えます。
社会的複雑性による競争優位の模倣が困難は人材育成に限らず組織全体の全てのプロセスに当てはまります。例えばチーム間の協力関係や意思決定の仕組み、リーダーシップのあり方、従業員の暗黙知の共有などは、単純に手順を模倣しただけでは再現できません。これらは個々の従業員の能力や価値観、さらには社内の歴史的経験や文化的背景と結びついているので、外部からはその全体像を把握することが極めて困難です。
更に社会的複雑性が高い競争優位は、特定の状況や文脈に依存して発揮される事が多いので、他社が同じ方法を実践しても同じ成果を得られるとは言えません。例えばある企業の独自のチームや評価制度が高い成果を生むのは、その組織特有の人材構成や信頼関係が前提となっている場合があります。これを外部企業が表面だけ似たような制度を導入しても、従業員の特性や関係性が異なれば同じような成果を出す事はできません。
このように社会的複雑性を伴う競争優位は、模倣の難易度が非常に高いので容易に模倣する事はできません。結果として企業は競争優位を長期間維持できる可能性が高くなり、単純な技術や設備の導入だけでは得られない強みが生まれる事になると言えます。企業戦略の観点からはこうした社会的複雑性を理解し活用することが持続的な競争優位の構築において重要になると言えます。
1-4.特許

特定の企業が「特許」で守られた技術力を有している場合も同じく容易に模倣する事ができません。
特許による競争優位は企業が保有する技術やノウハウを法的に保護する効果があるので、一定期間は競合他社からの模倣を防ぐ効果があります。特許によって守られた技術は、製品の性能向上や生産コストの低減、あるいは付加価値の創出につながるため、競争優位の重要な源泉となります。しかし特許は公的に出願・登録される過程で技術内容を公開する必要があるため、情報としては競合他社に漏れることになります。これにより理論上は特許内容を参考にした技術改良や設計変更が可能になり、競合他社から見ると模倣のハードルが下がるとも言えます。
このように特許化するという事は情報を公開するという事でもあるので、競合他社から見ると模倣しやすくなる事を意味します。何故なら特許に接触しない形で模倣される可能性もあれば、ライセンス契約(有償)により模倣されるケースもあります。また特許が切れれば完全に模倣されてしまう事になります。特許を取れれば一定の期間は模倣を防ぐ事ができるので、その間は模倣困難性は高いものとなりますが、情報の公開はリスクになります。
従って特許による競争優位は模倣困難性を高める一方で、情報公開のリスクも内包しています。企業はこのバランスを考慮し、技術の保護と活用の戦略を設計することで、持続的な競争優位を確立することが求められます。特許を取得した期間は、他社の模倣が法的に制限されるため、戦略的優位を最大化できる重要な期間となります。
経営資源の模倣がコスト上の不利となる理由:まとめ
上記の通り企業は競争優位の源泉となっている資源・能力を模倣される立場にあります。しかし競合他社が表面だけ模倣すると上記の通り失敗する可能性は高くなります。そのため他社の競争優位を模倣しようと考える時は、常にそれらの模倣困難性についても分析するようにして下さい。