2025年05月22日
目次
囚人のジレンマとは?
ゲーム理論の代表的な例が「囚人のジレンマ」になります。ゲーム理論とは自分と相手の利益を考えて最適な行動を決める為の理論になります。囚人のジレンマは自分と相手の両方に悩みをもたらすモデルになります。まず以下のマトリックスをご覧下さい。
1-1.囚人のジレンマのマトリックス
| 容疑者Bー自白する | 容疑者Bー自白しない | |
| 容疑者Aー自白する | (A=懲役5年・B=懲役5年) | (A=懲役なし・B=懲役10年) |
| 容疑者Aー自白しない | (A=懲役10年・B=懲役なし) | (A=懲役2年・B=懲役2年) |
上記のマトリックスは容疑者A・容疑者Bの行動と懲役年数の結果になります。容疑者Aが自白した場合、容疑者Bが自白すれば5年、自白しなければ懲役なしとなります。また容疑者Aが自白しない場合、容疑者Bが自白すれば10年、容疑者Bが自白しなければ2年となります。では、容疑者Aと容疑者Bはどのように行動すべきでしょうか。
上記のマトリックスは「囚人のジレンマ」の典型的な例になります。理性的に考えると両者が「自白しない」を選べば懲役2年ずつで済み、全体としては最も軽い結果になります。あなたがとても仲の良い信頼できる友人と意思決定をできるなら二人で一緒に「自白しない」を選択しますよね。しかしここで問題となるのは「相手の行動が読めない」という状況です。容疑者Aからすると、もし自分だけが自白せず相手が自白してしまえば懲役10年を科されるリスクがあります。同様に容疑者Bも同じジレンマを抱えています。そのためお互いが自分の利益を最大化するために合理的な選択をすると、両者とも「自白する」を選ぶことになります。これは最適な結果ではありませんが、裏切られるリスクを避けるための合理的判断です。自白すれば「懲役5年か懲役なし」のいずれかになり、自白しなければ「懲役2年か懲役10年」になるのです。いずれを選択するのが合理的なのかは明白ですよね。この構造こそが「囚人のジレンマ」であり、特にビジネスにおける協力と競争の難しさを理解するのに重要な概念になります。
1-2.相手を信用するメリット

相手を信用するメリットは成功すれば全体的な結果を最大化できるという点になります。
両者の合計結果を最大化するには相手を信用するのがベストです。何故ならお互いが自白しないを選択することでそれぞれ懲役2年、合計4年という最も短い懲役合計期間を勝ち取る事ができるからです。事前に話し合って協調した行動を取る場合、それぞれ自白しなければお互いが懲役2年となり、それぞれ自白するケース(お互いが懲役5年=合計10年)より罪は軽くなります。そのため2人の利害が一致するのは右下の「それぞれ自白しない。」が該当します。しかしこれだと2人は自分「個人」の利益を最大化したとは言えません。何故ならこの状況で相手を信用させて自分だけ自白した場合、自分は懲役なしという個人の最高結果を勝ち取る事ができるからです。つまりこの状況ではナッシュ均衡という概念が関係してきます。
「ナッシュ均衡」というのは相手の行動が固定されている場合は、自分だけ行動を変えてもそれ以上の利益が得られない状態を指します。つまり相手の戦略を前提として自分が最適な戦略を取っている状態です。囚人のジレンマにおいては、両者が「自白する」を選ぶケースがこれに当たります。何故なら相手が自白する状況で自分だけ自白しなければ、10年の懲役という最悪の結果を招くからです。そのためお互いに裏切られるリスクを避けるために「自白する」ことが最も合理的な行動とされます。しかしその結果、全体としては懲役5年ずつ(合計10年)と協調した場合の2年(合計4年)よりも重い懲役を受けることになります。このように「個人の合理性」と「全体の最適解」が必ずしも一致しない点こそが囚人のジレンマの本質であると言えます。現実のビジネスや国際関係においても、信頼の欠如により協力が難しくなり、互いに損をする選択に陥るケースが数多く存在します。
1-3.相手を裏切るメリット
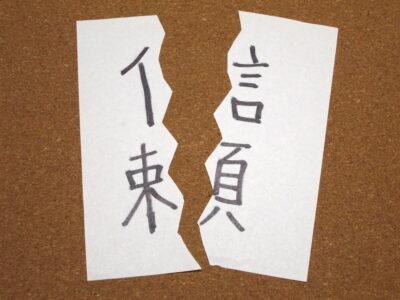
相手を裏切るメリットは成功すれば個人の結果を最大化できるという点になります。
相手を裏切ることで個人として最高の結果を実現することが可能になります。具体的には相手を信用させて「お互い自白するのは辞めよう。」と相手を説得し、その約束を裏切って自分だけ自白すれば、自分だけは「懲役なし」になる可能性があります。つまりそれぞれが自白しない場合は懲役2年となりますが、裏切ることでその2年すら「懲役なし」に変えられる可能性があります。そのため相手を信用するメリットは存在していても、裏切るメリットも同時に存在していると言えます。そのためお互いが相手を信用した場合はリスクを背負う事になるのです。相手が裏切れば自分だけ懲役10年となってしまうからです。そのためそれぞれに次のような考えが発生します。
それは相手を信用すべきか裏切るべきかという心の葛藤になります。このような状況では「裏切るメリット」と「信用するメリット」の間で心が揺れ動くことになります。合理的に考えると、自分が裏切れば最も良い結果(懲役なし)を得られる可能性があります。しかし一方で、協調を選んで相手に裏切られた場合には懲役10年という最悪の結果を背負うことになります。つまり囚人のジレンマでは、「自分が損をしないように行動すべきだ。」というインセンティブが働き、結果として両者が互いに裏切りを選択してしまうのです。これがナッシュ均衡であり、協調よりも裏切りが合理的と判断される所以です。そして相手が裏切る(つまり自白する)と分かっていれば、自分も自白しますよね。これが現実で発生する状態になります。ただし現実社会では相手との長期的な関係の中で信頼が形成されることで、協力が安定的に成り立つ場合もあります。ビジネスや国際交渉においても、必ずしも全員が相手の裏切りを想定する訳ではなく、信頼を維持する長期的利益が重視される場面も多くあります。
1-4.相手を信用しないメリット
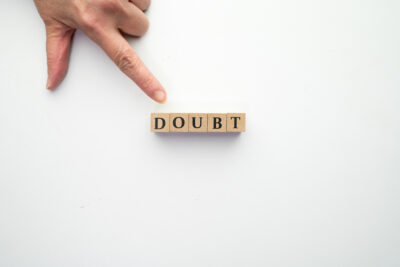
相手を信用しないメリットは個人として最悪の結果を防ぐ事ができるという点になります。
相手を信用しても相手が裏切れば最悪の結果となります。相手を信用しお互い自白しないという選択をしても、相手が裏切って自白すれば自分は懲役10年になります。よって相手を信用すればリスクが発生します。しかし仮に相手が裏切った時に自分も同時に裏切った(つまり双方が自白した)場合、それぞれの懲役は5年ずつとなります。これだと懲役10年は避ける事ができますよね。つまり相手を信用せず裏切って自白した場合は「懲役なし又は懲役5年」のいずれかの結果になるので、相手を信用して裏切られた場合の「懲役10年」という最悪の結果は回避する事ができます。そのため相手が裏切る可能性があると判断できる場合、または相手を完全には信用できない場合、相手が裏切るという前提で意思決定を下す方が合理的であると言えます。
ここで重要なのは裏切りが合理的な選択になるという事実です。囚人のジレンマにおいては、自分が裏切れば「懲役なし」か「懲役5年」という結果になり、相手の出方に関係なく「懲役10年」を避けることができます。つまり裏切りはリスク回避の観点から合理的な行動であり、ゲーム理論的には双方が自白する(裏切る)というという行動がナッシュ均衡であると言えます。しかしこの均衡は両者にとっての最適解ではありません。何故なら双方が協調して「自白しない」を選べば懲役2年ずつで済み、全体としてはより望ましい結果を得る事ができるからです。ここに「個人の合理性」と「全体の合理性」の衝突があります。この矛盾が示すのは、ビジネスの戦略や組織経営においては、相手をどこまで信用できるかが重要であるという事実になります。しかし相手を完全に信用するのが難しいのがビジネスという戦場でもあると言えます。
1-5.結果として非合理的な選択をする。

結果として囚人のジレンマのような状況では両者は非合理的な選択をしてしまう事になります。
つまりこの状況では囚人は「自白」という選択をします。何故なら自白すれば「懲役なし or 懲役5年」、自白しなければ「懲役2年 or 懲役10年」となり、自白する方が比較すると合理的な選択肢となってしまうからです。協力すればお互いが懲役2年を勝ち取れるのに、この状況で囚人達はそれぞれが合理性に基づいて自白という選択をします。結果、それぞれが懲役5年となり、協力し合った結果(懲役2年ずつ)より悪い結果となってしまうのです。これが囚人のジレンマです。
この「囚人のジレンマ」が示すのは、個人の合理的判断が全体の非合理的な結果を導くという事実になります。、ビジネスに置き換えれば、企業同士が価格競争を続けた結果として業界全体の利益が減少する状況や、国際政治における軍拡競争が典型的な例です。本来は協調した方が双方にとって利益が大きいのに、お互いを信頼できず「裏切り」を選ぶことで、より不利な結果を招いてしまいます。しかし現実社会では、一度きりではなく関係が長く続くことが多いので、その場合は信頼や評判の形成によって協力的な行動が促されることがあります。MBAで学ぶ経営戦略においても、短期的な合理性だけではなく、長期的な関係性や信頼構築をどう構築していくかが重要なテーマになります。そのため長期的に見れば裏切りという結果は企業を不利な立場に追い込む原因となります。
囚人のジレンマとは:まとめ
企業戦略でも囚人のジレンマと同じような状況が発生します。これは企業が相手と協力した場合に得られる利益より裏切る利益の方が高い場合に生じます。合理的な選択をするのは重要ですが、上記のコンセプトをしっかりと理解した上で意思決定を行う必要があります。そのためこの「囚人のジレンマ」というコンセプトはしっかりと覚えておくようにしましょう。