2025年05月10日
研究計画書の書き方
別記事「MBA研究計画書の書き方|作成前にやるべき5つの準備とは?」で解説した通りに研究計画書を書く準備ができたら、実際に研究計画書を執筆していく事になります。研究計画書は大きく分けて以下の三つの種類に分けることができるます。それぞれの書き方について解説します。
1-1.エッセイ型
1.内容
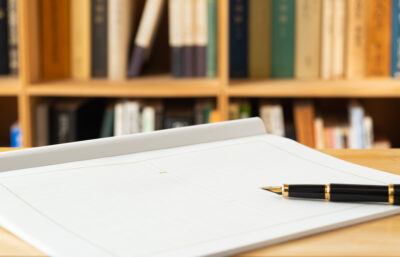
一つ目は「エッセイ型」になります。
基本的にビジネススクール(MBA)の研究計画書は「エッセイ型」が主流になります。具体的には「志望動機」「修了後のキャリアプラン」「過去の実績」「自己PR」などを書く書類になります。これに対して指定された字数で自分の考えを述べます。
またエッセイには「序論」「本論」「結論」の三つを書く必要があります。「序論」は書き出しであり「本論」は全体の要点、「結論」ではまとめを書きます。
2.書き方
まず書き方としては準備してきた内容を踏まえて「本論」と「本論の章数」をまとめて下さい。例えば志望動機で答えたい内容が三つあれば本論の章数は三つになります。そしてこれらの本論の前後の「序論」と「結論」を引き、残った字数を三つに割り、概ねその字数以内で話をまとめて下さい。仮に字数が合計1,000字で「序論」と「結論」に併せて100字程度を使うなら、残った字数は約900字なので、各章の文字数は約300字になります。あくまで目安に過ぎませんが、バランスが取れた文章構成になるよう、字数の配分はできる限りしっかり意識して下さい。次に本論の各章ではその章の結論を先に書いて下さい。そして「章の結論」→「理由・背景」→「例・根拠・データ」→「章の結論」の順に内容を書いていきます。例えば志望動機の一つの章の結論が「貴大学院は体系的なファイナンスのカリキュラムを有しているからだ。」という内容であれば、理由としては「体系的なファイナンスを学ぶべき理由・背景」が挙げられ、例・根拠やデータとしては「実際のカリキュラムの詳細(〇〇の科目がある等)とそれを受講する事で得られる効果」に言及する必要があります。そして結論を再度述べます。(しかし状況次第で各章の結論は省いても構いません。)この書き方を各段落でしっかり守って書いて下さい。最後に「序論」と「結論」は同じ内容にして下さい。「序論」は一般論から論文の要点までを書き、「結論」は繰り返し論文の要点を書きます。そして最後に締めの文章を入れて終了です。
3.注意点
上記が基本的な計画書(エッセイ型)の書き方になります。これだけ書くと非常にシンプルですが、実はこのエッセイが上手く書けずに苦戦する人は大勢います。また自分では上手く書けたと思っても、プロの目から見ると合格水準に達していないケースは多々あります。その理由は準備不足、例えば躓いた課題から感じた身に付けたい力が適切ではなかったり、課題の選択ミスだったり、論理的に意見を述べられていないケース等があります。
また他に多い失敗例としては一貫性がないことを述べていたり論理が弱いケースがあります。例えば過去の仕事と無関係な主張を展開しているケースなど等です。今までSEとして働いてきた人が、これから経営コンサルティングをやりたいからビジネススクールで学びたいと主張しても、その考えに至るまでの過程が不明確だと嘘で固めて綺麗事を並べただけだと思われてしまいます。むしろ教授陣はそのような嘘を見抜くプロなのでこのような書き方は絶対に避けるべきです。そのためエッセイ型は徹底した過去の自己分析と未来に向けた課題を論理的に書く必要があります。
またライティング力も高める必要があります。ライティングは主張を述べた後に理由と根拠を述べるものですが、このライティング力もエッセイ型には必要になります。(ライティング力については別記事で解説します。)よって別記事「MBA研究計画書の書き方|作成前にやるべき5つの準備とは?」で書いた通りにしっかり過去と向き合い内容を準備し、そしてライティング力を身に付けてから、上記をしっかり守って執筆するようにしましょう。
1-2.研究計画書型
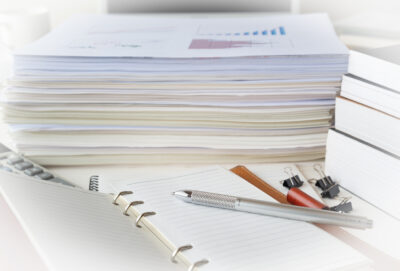
二つ目は「研究計画書型」になります。いくつかのビジネススクールは研究計画書型を採用しています。
むしろ言葉の定義として「研究計画書」というのはこちらが正しい定義になりますが、ビジネススクールの入試では研究計画書という名称の「エッセイ型(研究計画書)」が主流になります。研究計画書型を採用しているビジネススクールの方が少ないのが実態です。
研究計画書型も本質的にはエッセイ型と同じ書き方で大丈夫ですが、これにはしっかりとしたリサーチデザインを記述する必要があります。このタイプは字数が多いだけではなく、多くの先行研究を読む必要があるので、ここで簡潔に書き方を述べる事はできません。一般的にはエッセイ型と同じように書きますが、それに対して先行研究を入れていく必要があります。その意味で先行研究を読む所から始まるので、研究計画書型はできる限り一人で進めずプロと一緒に進めるようにしましょう。
その理由は既に修士論文を書いた経験を有する人や、特定の学会に所属しジャーナル等に論文を投稿した経験のある人以外は自力で作り上げるのが難しいからす。(ただしエッセイ型でも自力で作り上げるのは難しいのが現実です。)実際に大学院生となり研究を行う場合でも一人で進めるのは不可能ですが、それと同じです。(通常は指導教官+研究メンバーと一緒に議論しながらリサーチデザインを作ります。)そのためこのタイプの大学院を志望する場合は指導してくれるプロを見つけてから一緒に取り組むようにしましょう。
1-3.ハイブリッド型

三つ目は「ハイブリッド型」になります。
ハイブリッド型を採用しているビジネススクールも多くあります。ハイブリッド型は「エッセイ型」と「研究計画書型」が混ざったものになります。ハイブリッド型はエッセイ型で問われるような「志望動機」「修了後のキャリアプララン」「過去の実績」などと併せて「研究したいテーマ」を書くスタイルの研究計画書になります。このタイプの研究計画書を求めるビジネススクールも多くあります。
ハイブリッド型の研究計画書は、基本的にエッセイ型の部分は上記(1-1)と同じです。しかし研究テーマに関して言えば、研究計画書型(1-2)のように、先行研究を調べ抜き、具体的な研究方法まで設定する必要はありません。自分が研究したいテーマの先行研究を少し読む必要はありますが、その程度で充分になります。そのため「ハイブリッド型」は「エッセイ型+興味のある研究テーマを述べる。」程度で充分であると認識しておいて下さい。
またハイブリッド型も同じく先行研究に該当する部分は指導してくれるプロを見つけてから執筆して下さい。何故ならやはり既に存在しているテーマは望ましくないからです。できれば先行研究に目を通し既存の研究にはないテーマが書ければ理想です。
研究計画書の書き方:まとめ
以上が研究計画書の書き方と種類になります。エッセイ型・研究計画書型・ハイブリッド型を問わず、研究計画書の書き方というのは普通に生活していて身に付くものではありません。普通に生活していて急に泳ぐ事ができるようになったり、ピアノが弾けるようになったりしないのと同じです。それぞれプロの指導者から泳ぎ方やピアノの弾き方を学び、練習し、何度も失敗した後にようやくできるようになるものです。研究計画書の執筆もこれと全く同じです。そして研究計画書はビジネススクールの入試では最も重要な内容になります。そのためしっかり方法を学んでから執筆するようにして下さい。研究計画書の書き方でお悩みであればいつでもご相談下さい。