2025年05月14日
5つの業界構造
マイケル・E・ポーター氏は業界構造には五つの種類があると指摘しそれぞれの特徴を述べています。これらは以下の通りです。
1-1.市場分散型業界

「市場分散型業界」とは多くの中小企業が存在しており、主要なプレイヤーがいない業界の事です。
市場分散型業界は多くの中小企業が激しく戦っているという特徴があります。主要なプレイヤーとは多くのシェアを握る企業や、主要な技術などを有していない企業の事です。このような状態になる業界は、参入障壁が低かったり、また規模の経済が機能しないという特徴が挙げられます。しかしこのような業界で「集約・統合戦略」に成功すれば、大きな利益を獲得できる可能性があります。
市場分散型業界では、多数の中小企業が激しく競争を行っているので、価格競争やサービスの差別化が激しくなりやすい点も特徴であると言えます。そのため単純に新規参入するだけなら大きな利益を得るのは難しいと言えます。しかし逆に言えば、業界に主要なプレイヤーがいないため、戦略的にM&Aや提携・効率化などを進めながら拡大すれば、市場シェアを獲得しやすくなります。また業界のプレイヤー間での統合が進むと、価格競争からの脱却やブランド力の向上、効率の最適化といったメリットを享受する事ができるようになります。更に業界内で独自技術や差別化されたサービスを持つ企業が業界を集約すれば、競争優位を確立しやすく、長期的な競争優位の実現も可能になります。このように市場分散型業界は競争は激しいが戦略次第で大きな利益機会があると言う事が出来ます。
1-2.新興業界

「新興業界」とは新しい業界又は復活した業界の事です。
新興業界はまだ競争のルールや基本的なビジネスの方法が確立しておらず多くの機会があります。また先行者優位を確立できる可能性もあり、新興業界は参入する企業にとって魅力的な業界です。現代ではAIや再生医療の業界などが新興業界であると言えます。しかしこの新興業界は不確実性が高いという特徴を有しているので、常に戦略や方法を変更できる柔軟性が必要な業界であると言えます。
新興業界は市場の成長スピードが速く、技術革新や消費者ニーズの変化が頻繁に発生するので意図的戦略だけでは通用しません。(意図的戦略についてはこちらの記事「意図的戦略と創発戦略とは?MBAで学ぶ経営戦略の形成プロセスを解説」をご覧下さい。)そのため新興業界で先行者優位を活かすには、柔軟な変化と迅速な意思決定が求められます。また新しい市場セグメントやサービスモデルを開拓しやすい状態でもあるので、競合他社が参入する前に独自のブランド力や競争優位を築く機会があります。ただしリスクも大きく、新技術や需要が計画通りに進まない場合(こうなるケースが多い。)は損失も発生しやすいので資金や資源も柔軟な配分が重要になります。このため新興業界で成功する企業は、状況に応じて戦略を柔軟に変える能力、つまり柔軟性が求められます。このように新興業界は大きな成長機会がある魅力的な業界であると同時に、高いリスクがある不確実性の高い業界であると言えます。
1-3.成熟業界

「成熟業界」とは成長期を過ぎた業界の事です。
成熟業界の特徴としては、需要の上昇率が落ちていき、業界の利益率が全体的に低下していくという特徴が挙げられます。つまり既に製品・サービスが定着しつつある業界を指します。現在の日本では多くの業界が成熟業界になっていますよね。このような状態でもシェアを伸ばしていく事は可能ですが、一般的には新興業界ほどの成長性を見込む事は難しい業界になります。
成熟業界では市場が飽和状態なので、企業の競争方法は価格やサービスの差別化などに変化します。その結果、新規参入で大きなシェアを獲得する事は難しく、既存企業間での争いが中心となります。しかし、ニッチ市場の開拓や製品・サービスに高付加価値を付ける、ブランド力を強化するなど戦略的に差別化を図ることで、利益を維持・向上させる事ができる可能性は残されています。またコスト管理やオペレーションの効率化・顧客ロイヤルティの強化なども成熟業界で成功するために重要になります。更に業界内でM&Aや業務提携を活用して規模の経済を追求することも有効です。成熟業界は大きな成長は見込みにくい状態ですが、既存の企業にとっては安定的な利益確保や競争優位の維持が可能な魅力的な状態であると言えます。
1-4.衰退業界

「衰退業界」とは業界全体の売上が落ち続けている業界の事です。
衰退業界の特徴としては既に成長は見込めないので企業(特に赤字企業)は何らかの決断が必要であるという特徴があります。何故なら赤字の状態をずっと継続する事はできませんよね。このように衰退業界の企業には方向性の決断が必要になりますが、その決断には撤退も含まれます。しかし必ずしも全ての企業が撤退すべきである、という訳ではないので、慎重に将来計画を組み立てる必要があります。また同時にこの業界に新規参入するのは非常に難しいと言えます。既存企業ですら赤字の状態になっている事が多いので、新規参入が難しいのは当然であると言えます。
衰退業界では市場全体の需要が減少しているので、企業間の競争方法は主に既存顧客の奪い合いやコスト削減・効率化等になります。そのため事業の効率化や事業の見直しが重要になります。一方でニッチ市場や特定の地域に強みを持つ企業は、規模を縮小しても安定的に利益を確保することが可能です。また競合他社が撤退することで生まれる市場の空白を取りに行く戦略も考えられます。しかし業界全体の縮小傾向は変わらないため、新製品投入や新たな投資による成長を目指すのは難しく、長期的には収益性が低ければ撤退を余儀なくされるのが一般的です。このように衰退業界では柔軟で利益確保の戦略が企業の生き残りを左右する事になると言えます。
1-5.国際業界
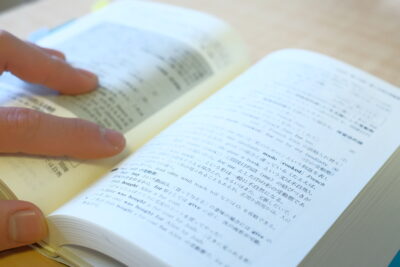
「国際業界」とは競争が国際化している業界の事です。
国際業界の特徴としては国際化が進んでおり企業の外部環境が変化し続けているという点が挙げられます。この業界は競合他社や顧客、競争のルールや戦い方などが変化し続けていきます。つまり国内だけで戦ってきた環境が少しずつ地球規模の環境に変化していきます。そのため常に国際的な競争に晒されているので変化の程度が極めて高くなります。結果として国内の環境だけではなく世界を相手にビジネスを進めていく必要に迫られるのがこの業界です。現代では世界中のあらゆる業界で国際化が進んでおり、これから多くの業界がその対応をしていく事になると考えられます。
国際業界では企業は為替変動や関税・法律・文化の違いなど、複雑な外部環境を常に意識する必要があります。そのため経営戦略や製品開発・マーケティング手法も国際的な視点で最適化することが求められます。またグローバル企業との競争や海外市場での機会や脅威を正確に把握するため、情報収集力も重要になります。更に海外現地法人と提携する事やサプライチェーンの最適化、多国籍チームのマネジメント能力なども企業の競争力を左右します。このように国際業界では戦略・オペレーション・組織という側面で国際的な適応力が問われる事になり、変化に柔軟に対応できる企業が持続的な競争優位を築くことができます。縮小を続けるマーケットに直面している多くの日本企業にとって、国際業界での成功は生き残りと成長に不可欠であると言えます。
5つの業界構造:まとめ
業界構造を理解する事は、企業が今後の戦略を策定する過程で必要不可欠な行為であると言えます。そのため自分が属する業界は勿論ですが、それ以外の業界構造も正しく分析できるようになりましょう。そしてMBAの受験では企業がどのような業界に置かれているのかを把握した上で、戦略の提案ができるようになりましょう。